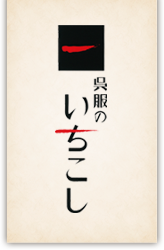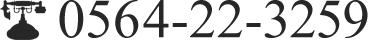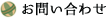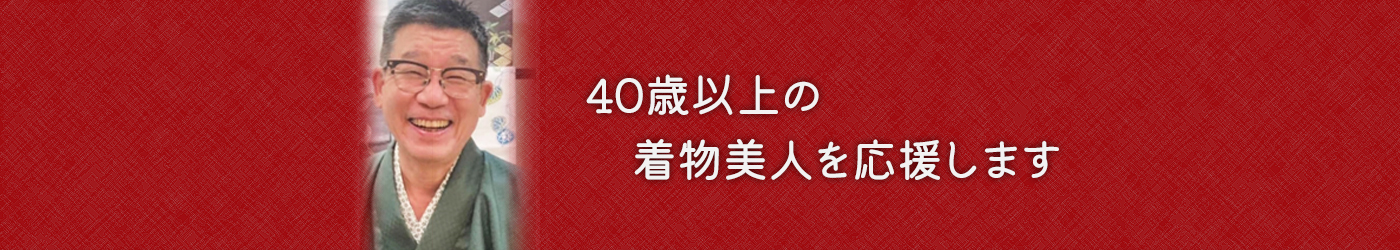豊田市民藝館での「絣の道」を観賞して。
ご紹介 2025年8月13日

Vol.3102
本日は、『豊田市民藝館での「絣の道」を観賞して。』です。
愛知県岡崎市の「呉服のいちこし」
和装を選ぶ楽しさと、纏う喜びを
全 力サポートいたします。
ご訪問ありがとうございます。
一昨日、雨の合間を縫って行って来た
のは、豊田市民藝館で開催されている
「海のシルクロード・絣の道」展。

布に模様を付ける際には、糸の
段階で色を付け織り上げる「絣」
と白生地に模様を付ける「染め」
があります。
「絣」は、インドを源流とし、
シルクロードを経てヨーロッパや
中国まで及びました。
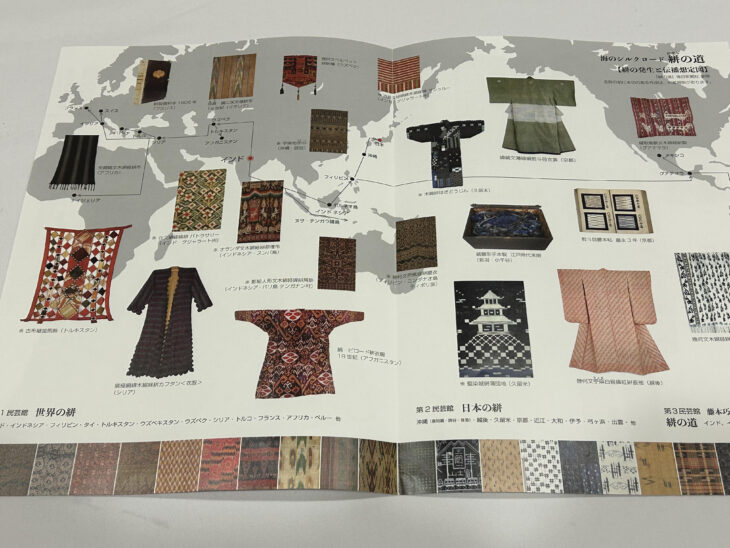
また、インドから南に下って
インドネシア、フィリピンなど
を経て沖縄へ伝わったのです。

沖縄で技術が花開いたのち、
弓浜、伊予、大和、近江、越後
など日本各地に普及したのです。

第1民芸館では、「世界の絣」として
インドやインドネシア、ラオス、タイ
シリア、ラオス、トルコ他からの作品を展示。
サリーなどの衣服は、勿論ですが
肩掛けや祭壇布に接馬布、宗教で
使用する旗などもありました。
主に、「経絣(たてかすり)」の展示品
が多く一部が「緯絣(よこかすり)」で
「経緯絣」は1~2点でした。
また、経糸は絹で緯糸は、木綿
などの混紡の作品もあり興味
深く鑑賞する事が出来ました。

そして、第2民藝館では「日本の絣」
を展示、まずは絣の原図「御絵図
(みえず)」が眼を引きます。
琉球王朝時代、王族や上級士族が
着用する着物を誂えるために王府
の絵師のよって描かれたデザイン画。
御絵図は、絣糸を作るために和紙
に原寸サイズで描かれ模様を布地に
複写したり、転写にも用いたようです。
そして、沖縄の絣では、芭蕉の糸
や苧麻糸が使用され着物が、多く
見られました。
久留米や弓浜では、木綿糸を使い
着物や布団地に子負い襦袢など
の普段の実用品が多く見られました。
越後製では、長着は勿論ですが
苧麻で経藍絣の振袖や経横絵絣
の祝着なども鑑賞できました。
日本製は、近代の作品と思われ
その精巧さは、目を見張るもの
が、ありました。
「絣」それは、人の手の温もりを
感じる事の出来る織物、今後も
注目していきたいです<m(__)m>
本日もお読みいただき誠に
ありがとうございました。
追伸・和服で、お困りのこと
なら何でもご相談、承り必ず
最善のお応えをいたします。